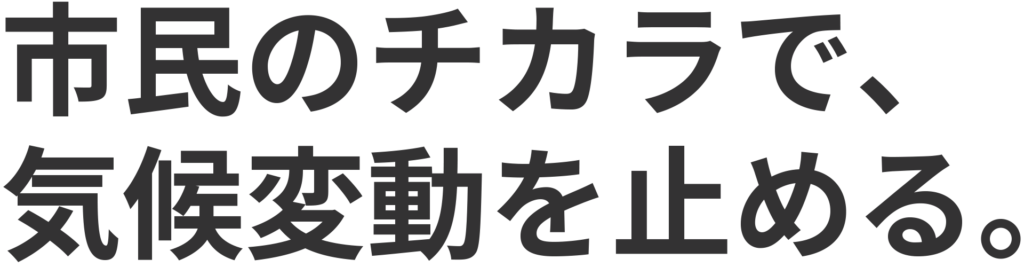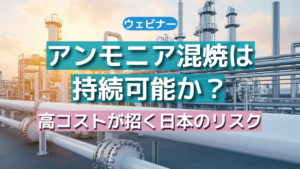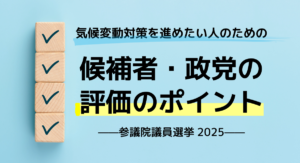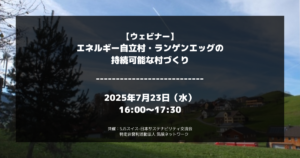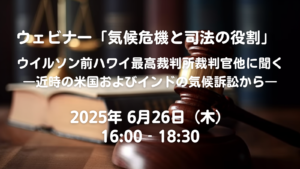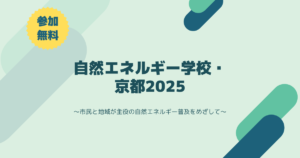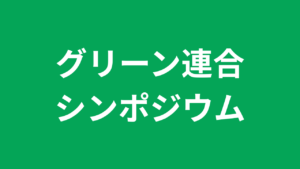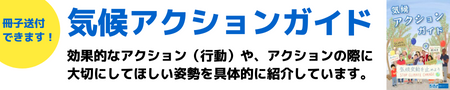新着情報
2025年6月18日(水)セミナー「電力システム改革の今後と再エネの未来」
2025-06-05
【意見書】扇町天然ガス発電所の建設計画 配慮書への意見提出(2025年6月2日)
2025-06-02
2025年6月12日(木)グリーン連合10周年記念シンポジウム
2025-05-21
気候ネットワークの活動
気候ネットワーク
について
特定非営利活動法人 気候ネットワークは、地球温暖化防止のために市民の立場から「提案×発信×行動」するNGO/NPOです。
今すぐアクション!
事務局からのお知らせ
2024-12-05
2024-07-31
2024-07-18